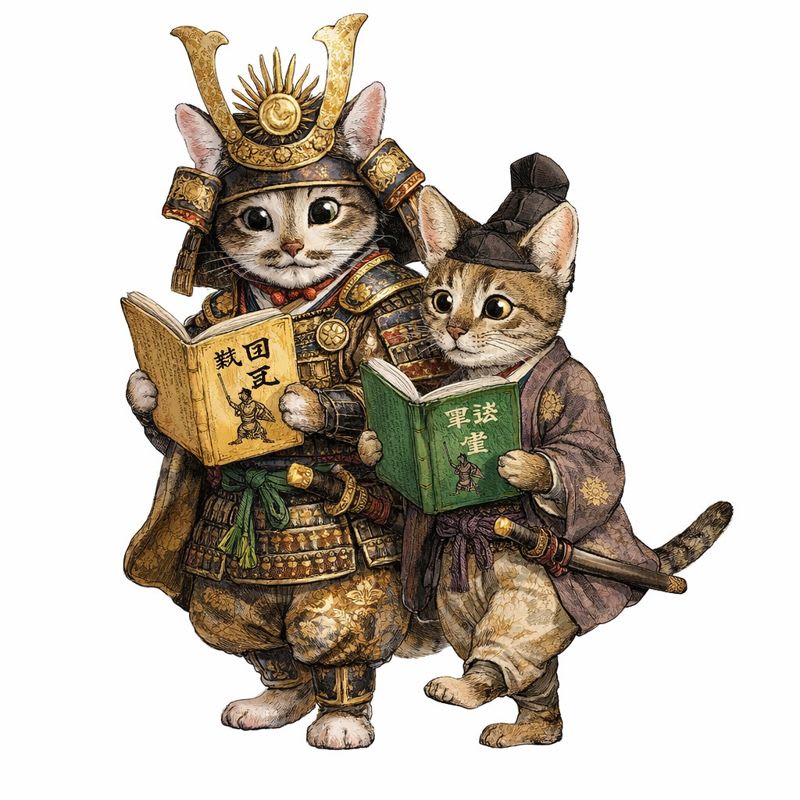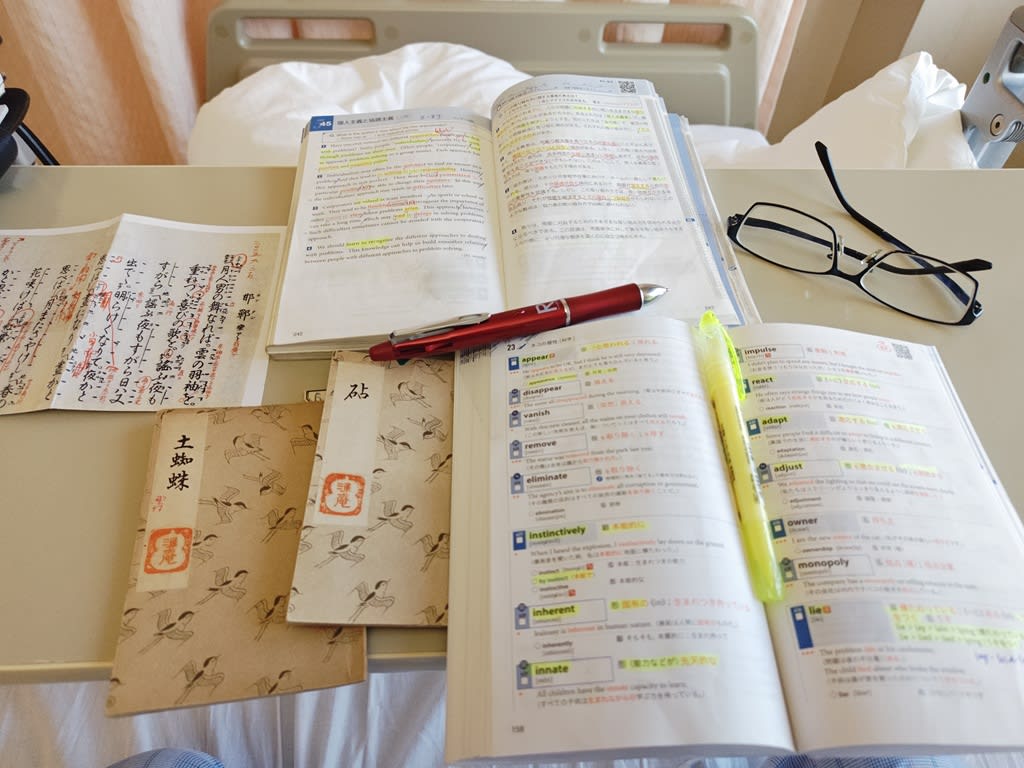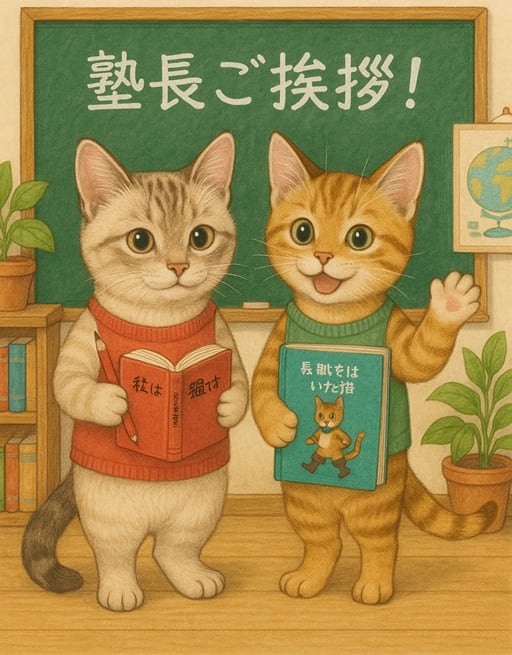塾長ブログ No.123 2025/5/6 目には青葉 山[A] 初[B]
塾長ブログ![塾長ブログ No.123 2025/5/6 目には青葉 山[A] 初[B]](https://res.cloudinary.com/eduone/image/upload/f_auto/q_auto/v1/microsite/prod/media/479/article/3b10f5cb-30d9-4ad9-ab44-05eb482aad56/479_t_5916_bfcxdc)
今日は国語の問題から。
タイトルの[ ]Aに鳥の名前を、Bには魚の前を入れなさい。
用意! チーン!
で、解けましたでしょうか?
今日の学ゼミ通信をお読みくださった方は簡単だったかもですね。
答えは、A:時鳥 B:松魚
これまた漢字の読み取り問題になります。
それぞれホトトギスとカツオです。
江戸時代の俳人、山口素堂(そどう)の作。
初夏の情景を視覚・聴覚、そして味覚で表した見事な俳句です。
見渡すと新緑、山からはホトトギスの「テッペンカケタカ」という声。
そして、初めて食べるカツオ。
季節の食べ物のことを「旬(しゅん)のもの」といい、そのはじめに出てくるものを「走り物」といいます。
現在では、カツオのたたきといって、周りをかるくあぶったカツオの切り身にネギやシソの葉などをたっぷり乗せて、酢醤油で食べます。
江戸時代の江戸っ子は、この初カツオにかなりこだわってました。
関西では、カツオを生で食べる習慣がなくせいぜい鰹節(かつおぶし)を食べていたくらいでした。
鎌倉を 生きて出でけん 初鰹 松尾芭蕉
神奈川の鎌倉沖で初めて捕れたカツオを快速船で江戸まで運び、先ず将軍様に納めます。
この時の値段は、カツオ1本が2両1分から3両。
当時の職人の1年分の手間賃です。現在の価格で、ざっと30万円~35万円。
刺身にして、蓼酢(たでず)か辛子酢(からしす)で食べたようです。
ま、それほど美味しいものではなかったと思われますが、初物を食べるということが、江戸っ子のかっこよさだったんでしようね。
そて、そろそろスーパーでも僕たちが買える値段のカツオが出回ります。
お刺身やタタキでいただきましょうか。