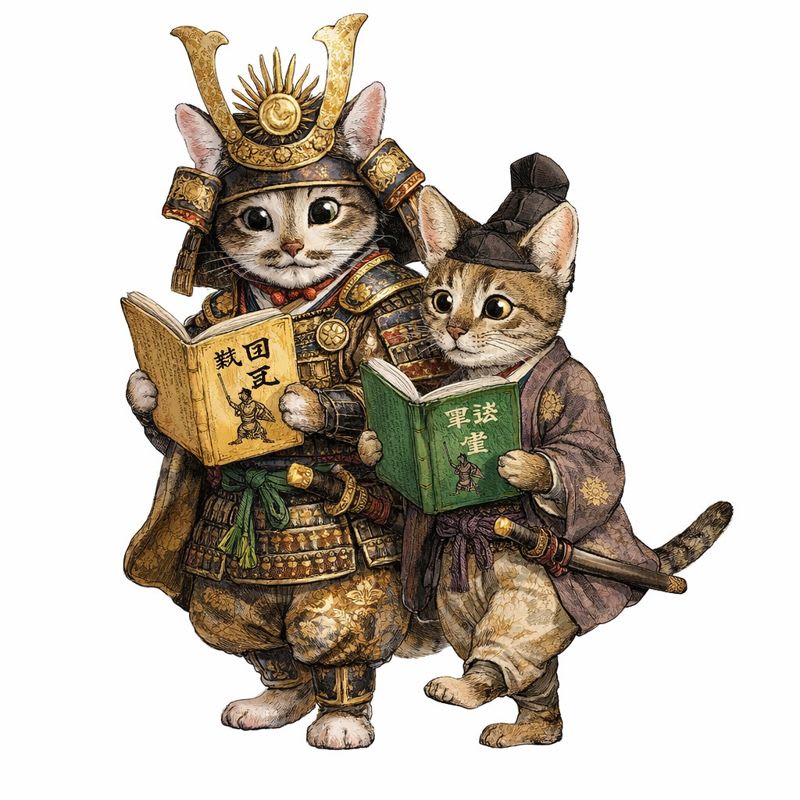塾長ブログ No.132 2025/7/8 想像力と国語力
塾長ブログ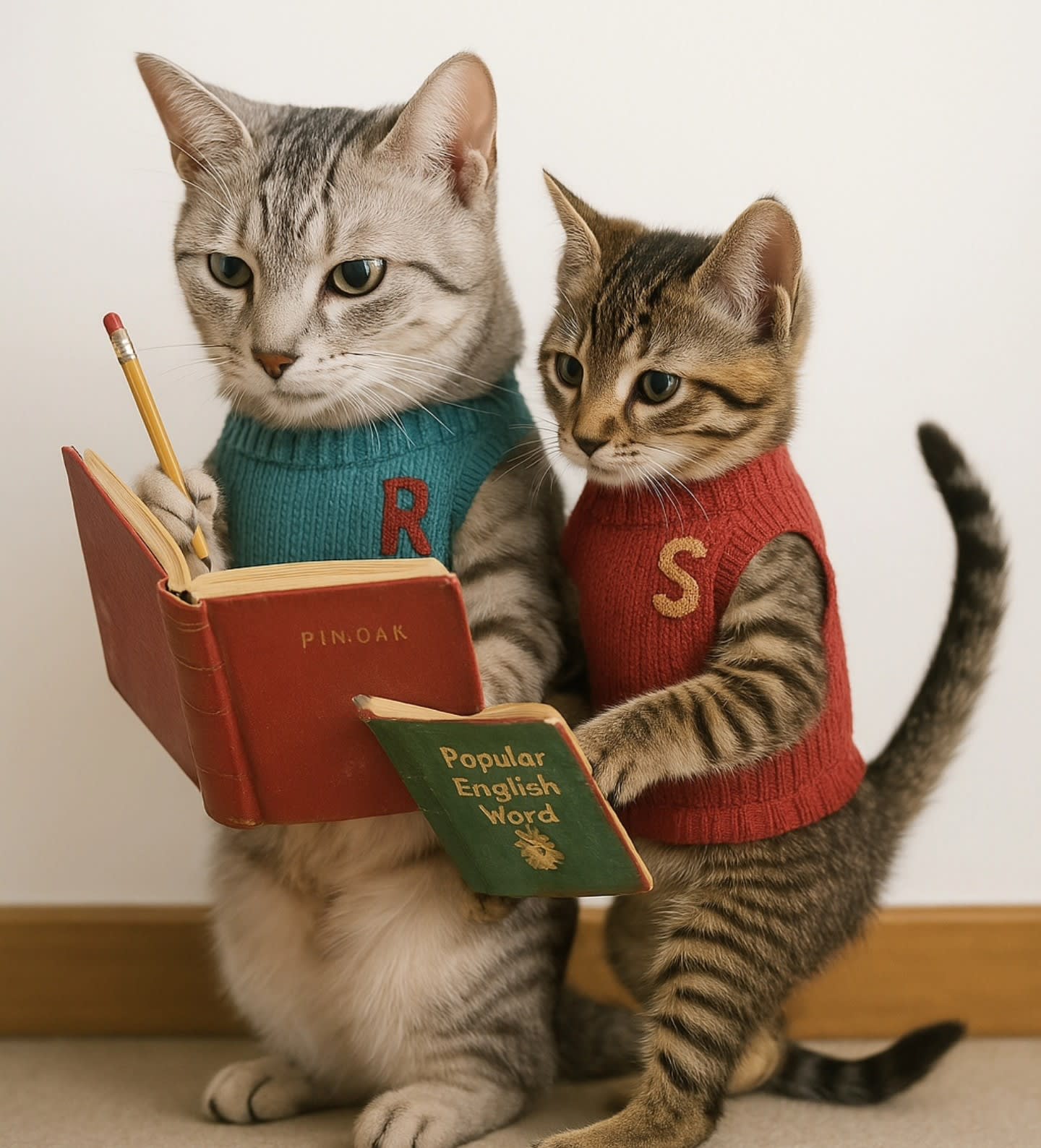
先週の水曜日、中学1年生の授業でうれしいことがありました。 「今週の塾長ブログ、読んでくれた?」と聞くと、一人の女の子が「英作文も書いてありましたよね。ノートに写しました」と。
ありがとうございます。 塾長冥利(みょうり)に尽きます。←意味は調べてみてね。
さて、今週は先週ご紹介した映画と原作の続きのお話です。 ThreadsというSNSに、次のような投稿がありました。
少し長いですが、ぜひお読みください。
「70歳老教員の独り言。
毎年、生徒の質が少しずつ変わってきている。
一斉指導が響かない。丁寧に説明しても、すぐに隣の子に聞く。 今説明したばかりのことなのに。
自分でよく考えようとせず、すぐに答えを求めて隣の子に頼る。 言葉だけで説明しても、なかなか理解が難しい。
作業になると、さらに難しい。 図や動画を使って説明しても、いざやらせてみると、できない生徒が多い。
経験が圧倒的に少ないせいもあるのだろうが、どうもそれだけではないようだ。
察するに、“想像力の欠如”のようなものではないかと思う。
私たちは本を読むことで、想像力を働かせてきた。
ラジオドラマにワクワクした時代もあった。
今では、想像しなくても答えがすぐにタブレットの画面に現れる。
レポートもコピー&ペーストであっという間に完成する。
スマホに守られながら育った子どもたちが、いま世の中に出てきている。
“想像力”は、どこへ行ってしまったのだろうか。」
僕もここ数年、ずっと「もやもや」と心の片隅に引っかかっていたことを、僕より少し先輩の先生が、まさにズバリと言葉にしてくださいました。
暗記力はあるけれど、それを使いこなせない生徒の割合が、少しずつ増えてきているように感じます。
もっとも、塾に通って「勉強しよう」という生徒さんばかりですから、そう多くはありませんが。
それでも、中学生コース・高校生コースの授業中どちらでも、「もっと頭を使って考えて」と声をかけることが、ここ数年増えてきました。
説明をして、例題も一緒に解いた後でも、自力で解けない。 そして再度説明している最中にも、それを聞かずに隣の子に答えを聞こうとする――。
まさしく、この元教師の先生がおっしゃるように、「考えることをしなくなった子どもたち」が、確かに存在しています。
先週観た映画『国宝』。 今、原作を少しずつ読み返しています。 映画も素晴らしかったですが、やはり原作のほうが、作者の想いや背景がより深く伝わってきます。
書かれていることから「自分で想像する」という作業が必要になりますが、それが楽しいですし、読書の本当の喜びだと思います。
国語が苦手、もしくは嫌い。 あるいは、定期テストのように範囲の決まった問題は解けても、実力テストではなかなか得点できないという人もいますね。
次回は、「では、どうすれば想像力がつくのか」について、お話したいと思います。