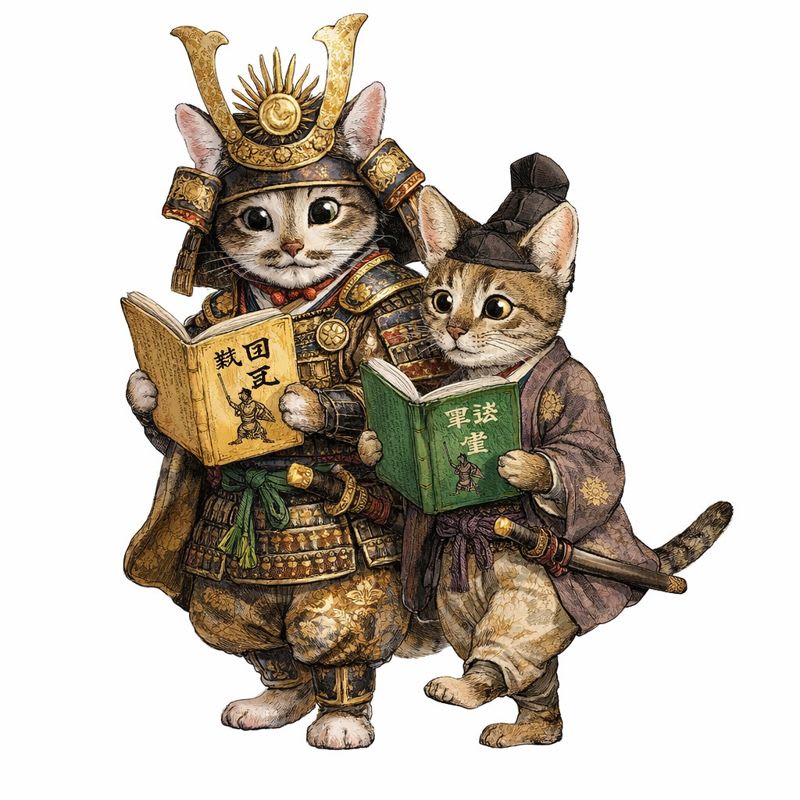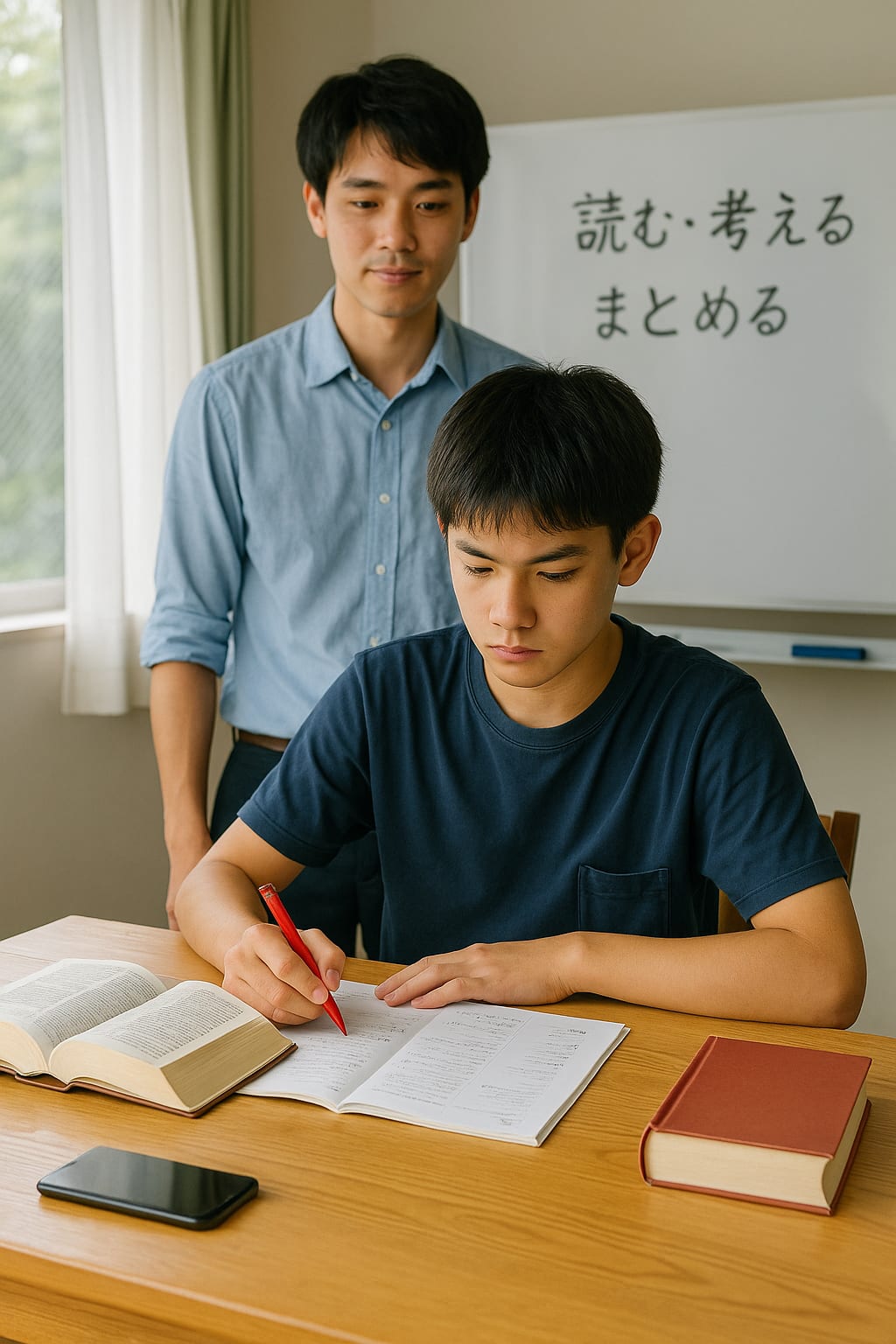塾長ブログ No.134 2025/7/22 想像力を身に付けないと・・・
塾長ブログ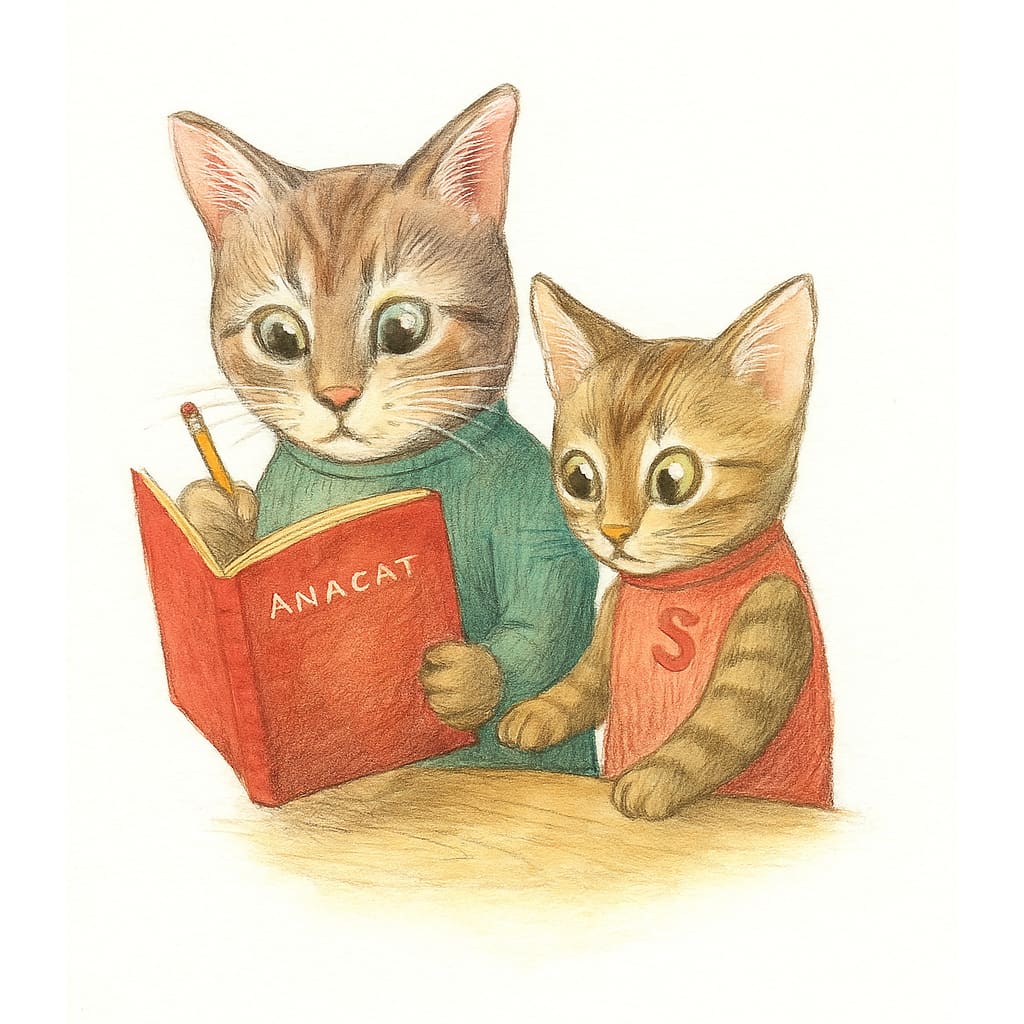
『ごんぎつね』が読めない小学生が増えてきた
40年間、国語を教えてきた僕にとって、これは少々ショッキングなタイトルでした。
記事の内容はこうです。
ごんが兵十の母親の葬儀に出くわす場面。
兵十の家には村人たちが集まり、葬儀の準備をしている様子が描かれています。家の前では、村の女たちが大きな鍋で料理をしている――その描写が、次の一文です。
〈よそいきの着物を着て、腰に手ぬぐいを下げたりした女たちが、表のかまどで火をたいています。大きななべの中では、何かぐずぐずにえていました〉
この「何か」という表現は、作者・新美南吉が、ごんの目を通してその場の様子を描いたからでしょう。
つまり、葬儀に集まった村の女性たちが正装をして、大鍋で参列者に振る舞う料理を作っている――ということが、常識的に読み取れるはずです。
先生もそう考えて、生徒たちに「鍋で何を煮ているのか?」というテーマで班に分かれて話し合わせました。
ところが、生徒たちから返ってきた答えは、次のようなものでした。
「兵十の母の死体を消毒している」
「死体を煮て溶かしている」
少し長くなりましたが、そういう記事でした。
「そんな、まさか」と思い、高校生の授業で同じ質問をしてみました。
返ってきた答えは――
ごんを煮ている
焚き木を煮ている
お母さんの好きなご飯を作っている
……さすがに国語コースの授業では正解が出ましたが。
2022年度、文部科学省は新学習指導要領の中で、国語のカリキュラムを大きく見直しました。
従来、高校で必修だった「国語総合」は、「言語文化」と「現代の国語」に分かれました。
「言語文化」は、文学作品や古文・漢文など、これまでの国語の学びを踏襲したもの。
「現代の国語」は、契約書の読解やデータの読み取りなど、実社会で役立つ文章を扱うものです。
大学入学共通テストにも、「評論・小説・古文・漢文」の4題に加え、資料を読み取り答える新傾向の問題が登場しています。
こうした変化の背景には、グローバル化の進展があるのでしょう。
インターネットによって、ビジネスからエンタメまで、国境の垣根は急速に消えつつあります。
世界が求める「読解力」を、日本の子どもたちにも身につけさせなければ、国際競争に取り残される――そんな危機感が透けて見えます。
だからこそ、英語でも日本語でも、ビジネスパーソンが使うような“実用的な”文章を読む力を育てようとしているのでしょう。
けれども今、そもそも読解力以前の「基礎的な力」が、大きく失われつつあるのではないでしょうか。
登場人物の気持ちを想像する力
別の出来事と結び付けて考える力
物語の背景を思い描く力
――こうした力が、子どもたちの間だけでなく、大人の間でも弱くなってきているように感じます。
たとえば、「能登で地震が…」や「私は米を買ったことがありません」と発言する人。
それを聞いて、悲しむ人や怒る人がいるかもしれない――そんな想像ができないのです。
自分の言動を客観視する「批判的思考」もまた、薄れているのではないでしょうか。
2014年9月10日号の New York Times に、アップル創業者スティーブ・ジョブズのこんな興味深い発言が載っていました。
“So, your kids must love the iPad?” I asked Mr. Jobs, trying to change the subject.
The company’s first tablet was just hitting the shelves.
“They haven’t used it,” he told me. “We limit how much technology our kids use at home.”
(「それで、お子さんはiPadが大好きなんですね?」と話題を変えようと尋ねました。Apple初のタブレットがちょうど発売された頃でした。
「まだ使っていません」と彼は答えました。「うちでは、子どもが家でテクノロジーを使う量を制限しているんです。」)
ジョブズ自身も、こうしたデジタルテクノロジーの急速な発展が人々に与える影響について、10年前の時点で危惧していたのかもしれません。
タブレット、動画、デジタル教材……今、私たちのまわりはそうしたものであふれています。
紙の教材は年々減ってきました。
でも僕は、この「想像力の欠如」と、紙からデジタルへの移行が無関係ではないように思うのです。
本来、文章は、文字を通して“頭の中で絵を描く”作業です。
紙の教材には、そうした力を引き出す働きが、きっとある。
このシリーズは今回で終える予定でしたが、もう一回だけ。
次回、「紙教材のすばらしさ」について、僕なりの考えをまとめてみたいと思います。