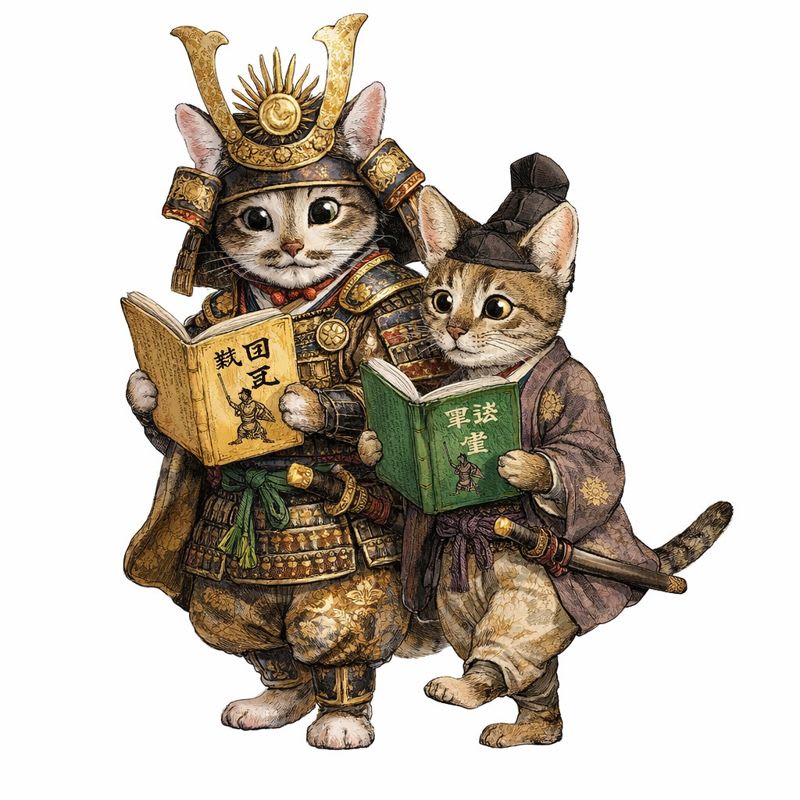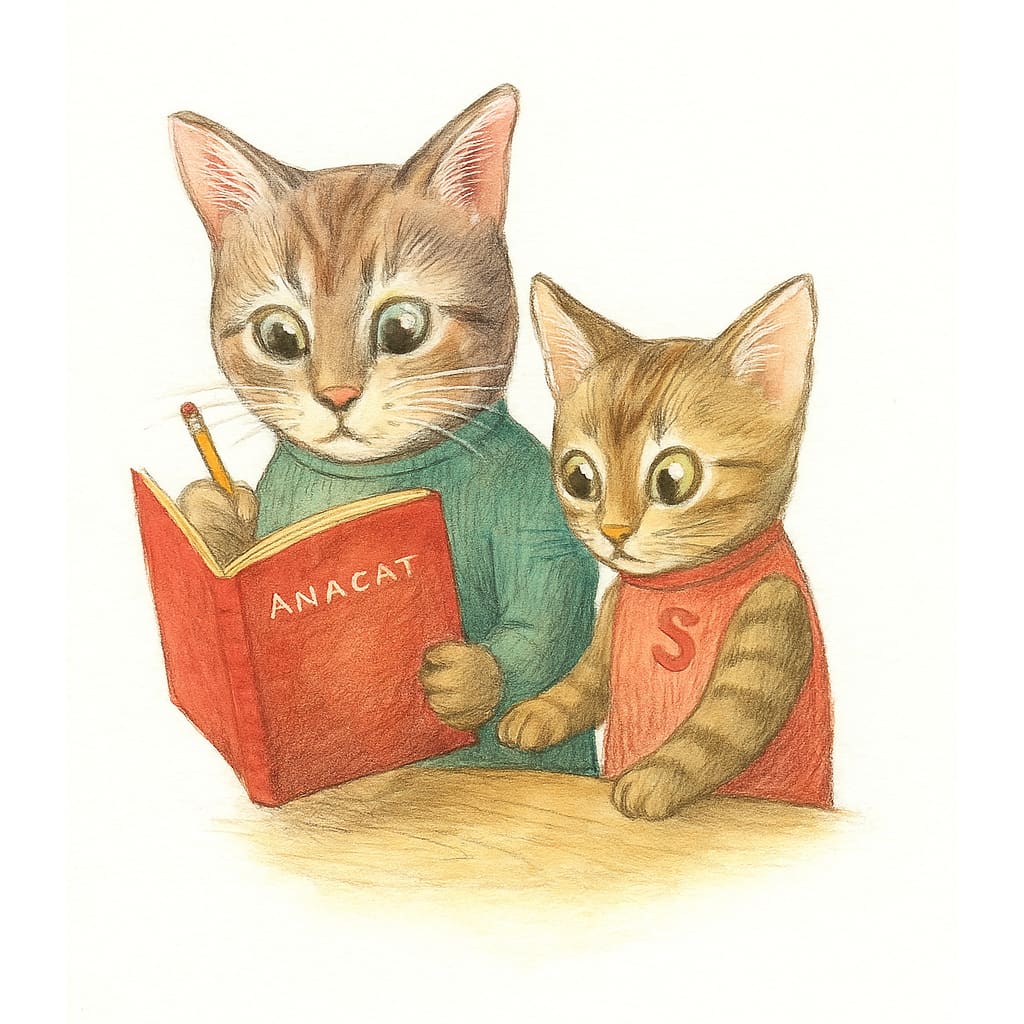塾長ブログ No.135 2025/7/29 読む・考える・まとめる――学びの原点へ
塾長ブログ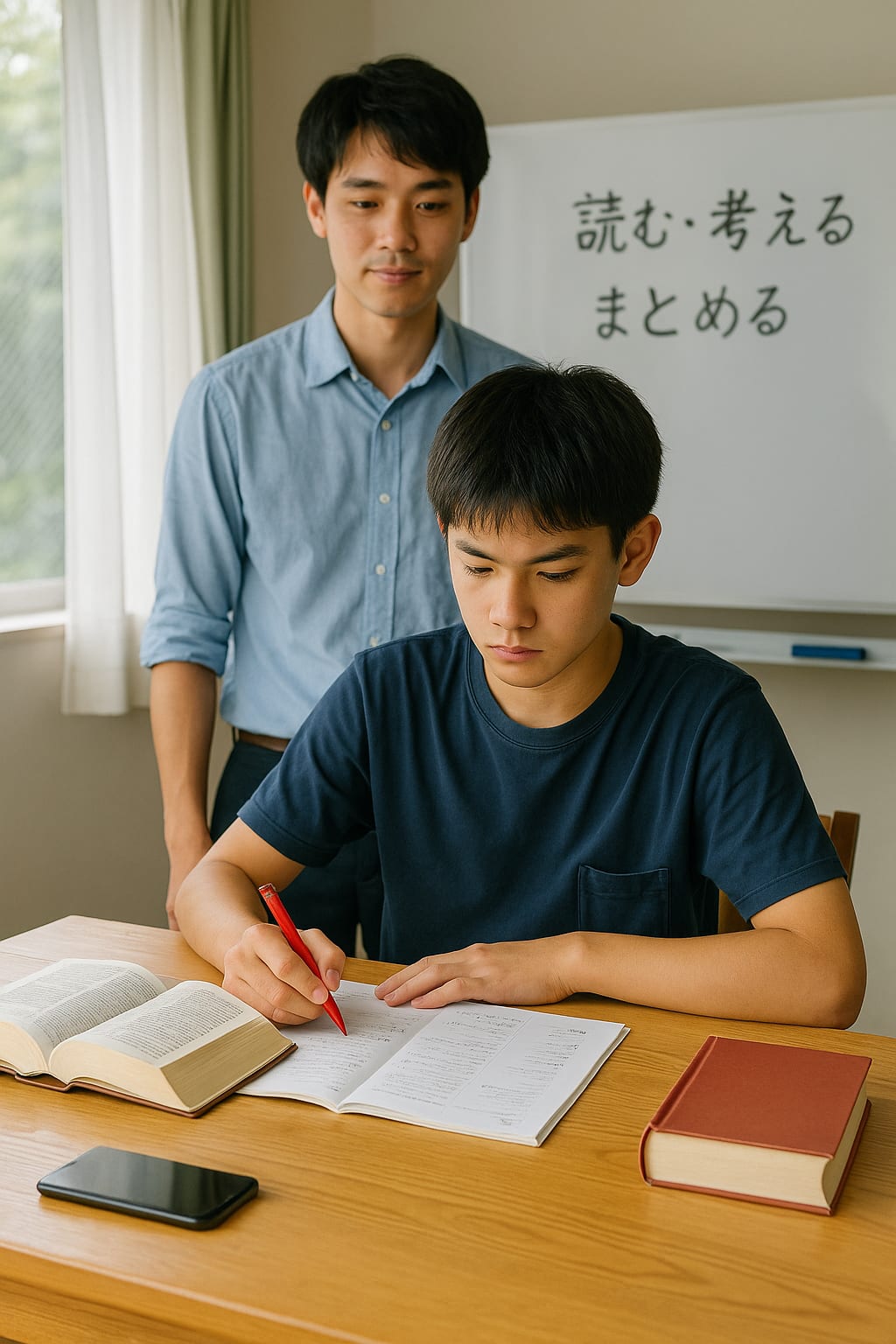
ここ数回の塾長ブログでもお伝えしてきましたが、いまの子どもたちにとって「国語力」の低下は、単なる教科の問題にとどまらず、学び全体の土台に関わる深刻な課題です。
テスト問題には、設問や文章の中にたくさんのヒントが隠されています。それを読み取り、理解し、活かすには、語彙力・読解力・論理的思考力といった「言葉の力」が欠かせません。
さらに、スマートフォンを使えば情報はすぐに手に入りますが、それを自分の考えとして整理・構築するには、また別の力が必要です。
大学受験や入試で問われているのは、まさにこの「思考力としての国語力」です。そしてそれは、大学進学後や社会に出てからも通用する、本質的な学力なのです。
学窓社ゼミの大学生講師たちは、こうした力をすでに身につけています。
・締め切りを自ら設定し、
・その期限までに何をどれだけ準備するか逆算し、
・自分に今足りていないものは何かを見極める。
そして、「そのために今、何をすべきか」を考え、最善の行動を取る。
彼らは大学受験期から、そうした勉強に向き合ってきたのです。
夏期講習会で単に学習内容を教えるだけでなく、「勉強の方法」や「想像力の育て方」についても彼らが生徒さん達にお伝えできればいいなと考えています。
想像力をつけるために必要ものの一つが、読書の大切さです。できればデジタルではなく、活字の本をおすすめしたい。
デジタルでは情報を「知る」ことはできても、「考える」「感じる」ところまでは届きにくい。
活字の読書では、文章の行間から筆者の思いや背景をくみ取る力が育ちます。これこそが、目に見えない「国語力」の核になるのです。
そしてもう一つお伝えしたいのが、紙教材の素晴らしさです。
問題を解きながらページをめくる、手を動かして書き込むといった体験は、思考の定着に大きく貢献します。
語彙力を高めるためにも、できれば紙の辞書を使って言葉にじっくり向き合ってほしいと思います。
少なくとも、タブレット端末で一問一答のように情報が一瞬で出てくるタイプの電子辞書ではなく、語義の違いや用例まで丁寧に載っている学習向けの電子辞書を使うことが大切です。
言葉を「引く」という行為そのものが、学びにつながるのです。
特に中学3年生と高校生には、夏期講習会の中で、こうした力を育てるための実戦的な講義を行っていく予定です。
最後にもう一つ。
スマホを触る時間が長すぎると、情報はただ断片的に頭に入るだけで、深く考えることができなくなります。SNSなども同様です。便利ですが、依存すると自分の思考の軸を持てなくなることもあります。
この夏、プチスマホ断捨離にチャレンジしてみてください。