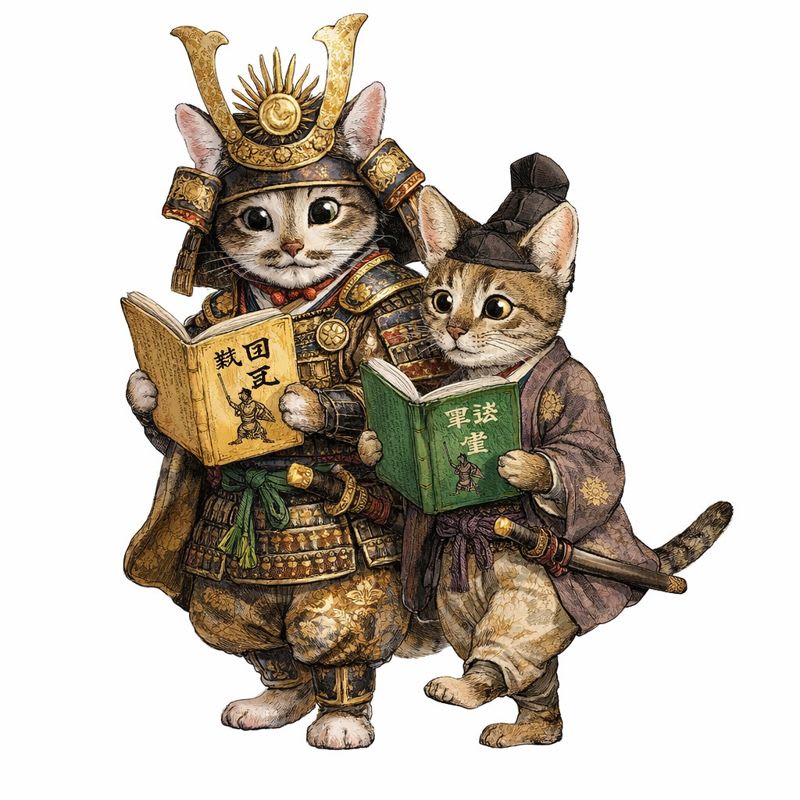塾長ブログ No.141 2025/9/30 耳袋
塾長ブログ
先週の高校三年生の国語の授業では、志賀直哉の「灰色の月」を題材にした大学入試現代文実戦問題を解説。
舞台は1945年10月、戦争直後の東京。 焼け跡の残る街と、そこで懸命に生きる人々の姿が淡々と描かれた名文です。
本文には「買い出し」「闇市」という言葉が出てきます。授業中、いつものように生徒さんたちに問いかけました。
僕:「買い出しはどうすること?」
生徒さん:「買い物」
僕:「じゃあ、闇市は?」
生徒さん:「市場」
僕:「文中に“リュックの中に壊れやすい物がある”とあるけど、これは何だと思う?」
生徒さん:……。
僕:「卵だよ」
今の生徒さんたちには、どうしても実感がわきません。
買い出しも、闇市も、卵も。
戦中から戦後にかけての配給制度では、最低限の食料しか手に入りませんでした。
だから人々は、満員の汽車に揺られ、農村へ出かけて食べ物を分けてもらったのです。それが「買い出し」です。
そして都市には、配給だけでは足りない人々が集まり、自然発生的に「闇市」が生まれました。
怪しさと活気が入り混じる場所で、人々は必死に生き延びようとしました。
卵と聞いても、生徒さんは首をかしげるばかりです。
そこで少し話を広げます。1950年頃、卵10個は160円ほど。
今は300円前後ですから、数字だけを見ればそれほど変わらないように思えます。
しかし当時の大卒初任給は5,500円。卵10個が今の価値にすれば4,000円ほどに相当します。
病気見舞いの品として重宝されたのも当然でしょう。
こう考えると、買い出しで手に入れた卵を大切に抱えて帰る人の姿が浮かんできます。
病気がちな妻や子どものために。寝たきりの年老いた親のために。
志賀直哉の文章の背後には、そんな人々の切実な思いが透けて見えるのです。
授業をしていると、こうした時代の知識は、生徒さんたちにはほとんど馴染みがないことに気づかされます。
しかし、言葉の背後にある空気を感じ取ることこそが文学の醍醐味です。
そして、こうした一見雑学のような知識が、実は受験においても大切になってきます。
耳袋――人から聞いたことや、ちょっとした知識を袋に入れていくように心に留めておくこと。
学びとは、そうした小さな積み重ねの中で深まっていくのだと思います。続きは、また次号で書いてみましょう。