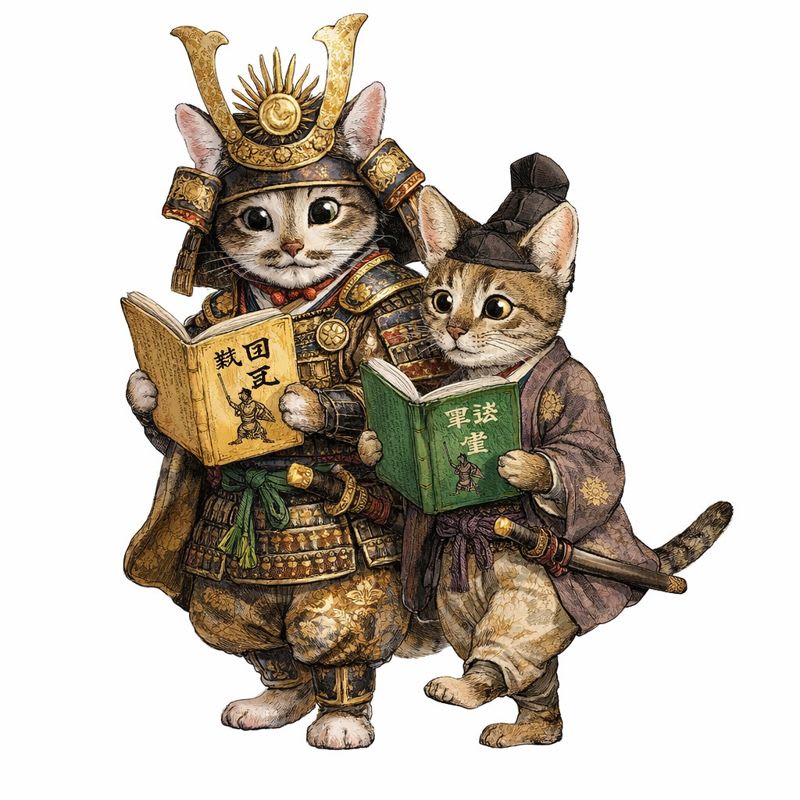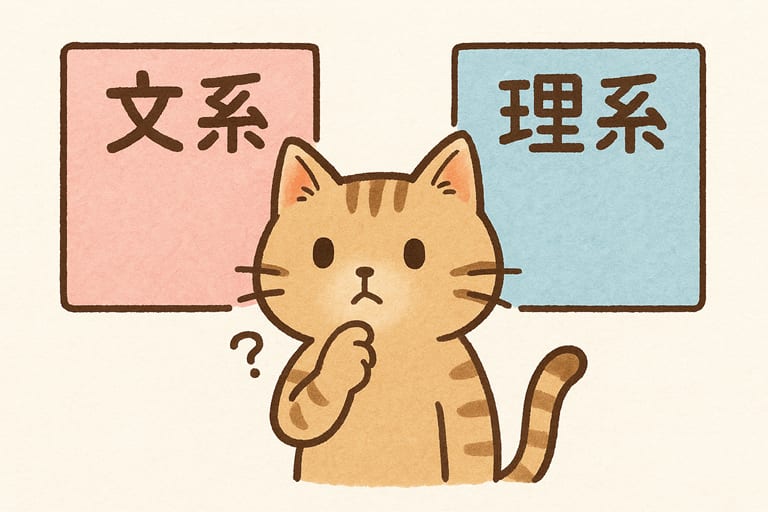塾長ブログ No.142 2025/10/07 続・耳袋
塾長ブログ
先週のブログのタイトル『耳袋』。
これは、根岸鎮衛(ねぎししずもり)の江戸時代の随筆。
鎮衛は、江戸時代中期から後期にかけての旗本。勘定奉行、南町奉行を歴任した。
『耳袋』は江戸時代の人々の好奇心が生み出した逸話集だった。日常の中で「なぜ?」と感じたことを集め、書き留めたものが、時を超えて僕たちに伝わっている。こうした知的な遊び心を、現代の文章で見事に受け継いだ人が、作家であり演劇評論家の戸板康二先生だと思う。
高校生の頃、僕は先生のエッセイや劇評を読み、その品のある文章に強く惹かれた。代表作の『ちょっといい話』には、何気ない日常の中にある人の温かさや、小さな出来事に宿る知恵が描かれている。『耳袋』が江戸の雑学の宝庫だとすれば、『ちょっといい話』は昭和の雑学を現代的な感性で語り直したものだ。どちらにも共通しているのは、「知ることの喜び」と「日常を少し豊かにしてくれる雑学の力」だと思う。
大学入学後の僕は、戸板先生の文章に導かれるように神保町の古書街を歩き、歌舞伎座で芝居を観た。浅草の蕎麦屋で、エッセイに登場したように天ぷらそばの種物でお酒を飲んだこともある。活字の向こうに広がる世界を追いかけたあの頃の自分を思い出すと、知ることそのものがすでに冒険だった。
人はよく「あの人は雑学家だ」とやや否定的に言う。でも、雑学とは本来、正しい情報の集まりであり、それを自分なりに解釈してこそ知恵になる。僕は、古今東西のさまざまな雑学を知ることが、どれほど人生を豊かにするかを実感してきた。「カノッサの屈辱」や「ボストン茶会事件」「宮中某重大事件」といった言葉の背景を調べたくなるのも、好奇心があるからだ。大学入試問題に出てきた作品を読んでみたくなることもある。そんなとき、学ぶことが心の栄養になると感じる。
長年、生徒さんの指導をしてきて思うのは、成績の伸びる人ほど好奇心が旺盛だということだ。中学生の授業でも、僕はできるだけ「考えてみて」と声をかけるようにしている。与えられた知識をただ覚えるだけでは、やがて限界がくる。暗記力だけで乗り越えられるのは中学生までで、そこから先は考える力と知りたいという欲がものを言う。
少し時間はかかっても、好奇心は人を育て、やがて生きる力となる。『耳袋』を書き残した根岸鎮衛や、舞台の灯を見つめ続けた戸板先生のように、僕もまた、生徒さんに「知る喜び」を伝え続けていきたい。好奇心の火を絶やさずに学び続けること――それが、僕の塾での教育の根幹であり、人生の願いでもある。