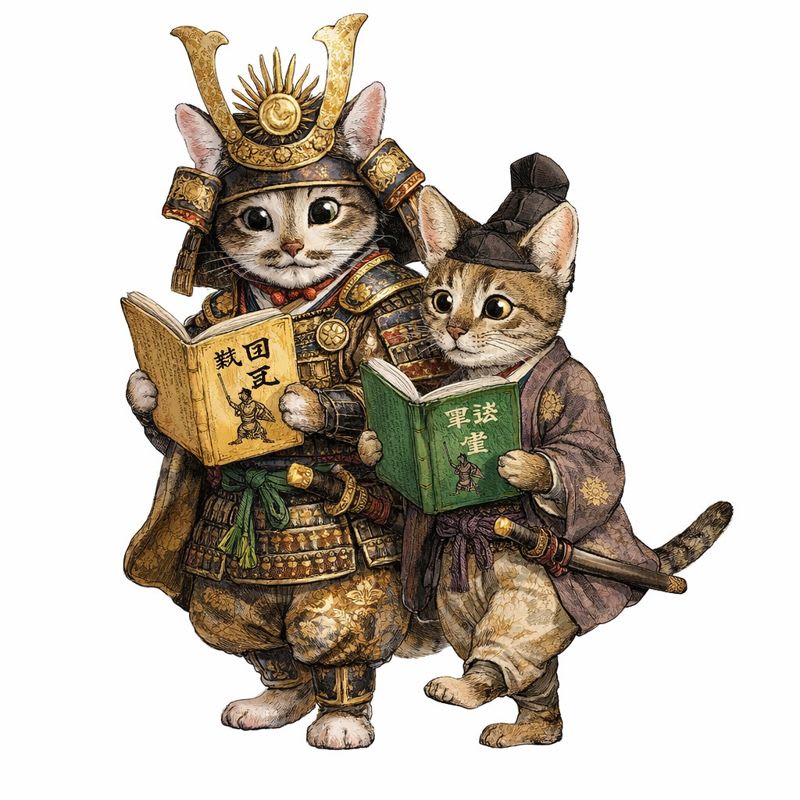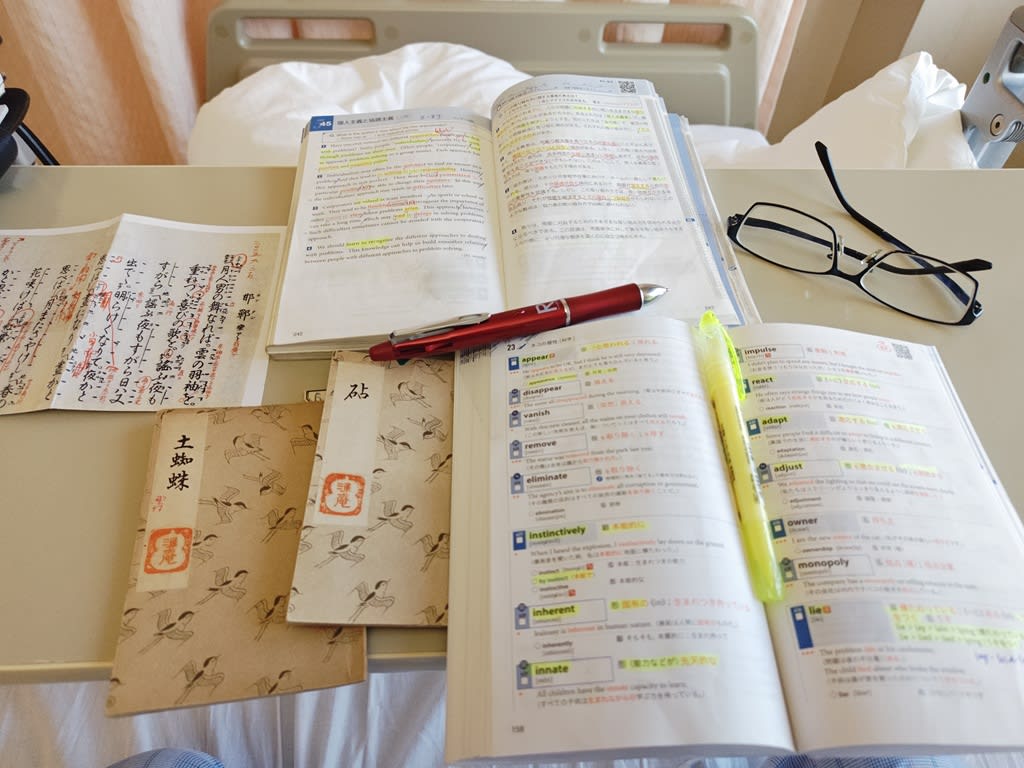塾長ブログ No.143 2025/10/14 文理のあわいにある力
塾長ブログ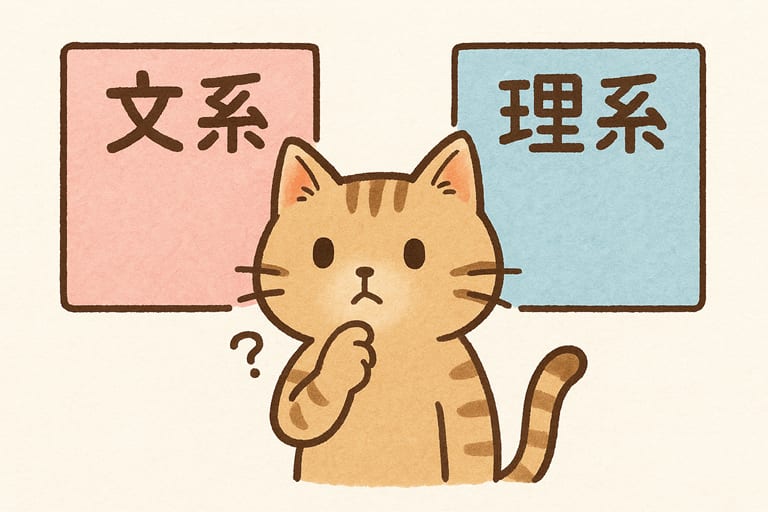
高校1年生の2学期になると、多くの学校で文系・理系の選択があります。
これによって、2年生以降に勉強する科目が変わりますので、いわば大学入試への第一関門といえるでしょう。
では、この文理選択は何を基準に決めればいいのか。
僕の場合は、中学生のころから数学がからっきし苦手で、それに伴って理科の物理・化学分野も好きになれませんでした。
これはもう、必然的に文系行きです。
国語と英語が得意で、社会が好きだったのも決め手でした。
我が家は、僕が文学部国文学科。
家内も文学部国文学科、息子は文学部日本史専修と、そろって文系。
文理の選択は生まれながらにして決まっているのか。
伯母は医学部を出て医者をしていましたし、弟一家の男性陣は獣医師。こちらは完全に理系。
遺伝子で決まるのか、生活環境で決まるのか――さて、どうなんでしょうね。
数学も高校では一応やりましたが、好きではありませんでした。
毎回、必死にチャート式の問題と解答を丸暗記して、なんとか欠点を免れていたという成績。
ですから今でも、数学や物理、化学に取り組んでいる生徒さんたちを、こっそり尊敬しています。
いや、あんな数式や図形がシャープペンシルの先っちょから次々と出てくるのを見ていると、ほんとに畏敬の念を覚えます。
さて、2025年のノーベル賞発表が10月6日(月)の生理学・医学賞から始まりました。
物理学賞は7日(火)、化学賞は8日(水)、文学賞は9日(木)、平和賞は10日(金)、経済学賞は13日(月)と続きました。
今年の生理学・医学賞は大阪大学の坂口志文博士、化学賞は京都大学の北川進博士が受賞。
分野は異なりますが、お二人に共通しているのは「京都大学で学ばれた」という点です。
ノーベル賞受賞者のうち日本人はこれまでに77名。
そのうち東京大学卒が21名で最多ですが、自然科学(物理・化学・生理学・医学)分野に限ると、72名中京都大学が20名、東京大学が18名。
理系の二次試験に難しい国語を課してきた京都大学の「自由な発想を育む伝統」が、こうした成果につながっているのかもしれません。
考えてみれば、文系と理系の境目というのは、実はとてもあいまいです。
文学的な感性をもつ科学者もいれば、論理的な思考力をもつ作家もいる。
京都大学の湯川秀樹博士や、東京大学教授の寺田寅彦博士は、一流の物理学者であると同時に、優れた随筆家としても知られています。
科学を突きつめるには、豊かな想像力と感性が必要であり、文学を深く理解するには、論理的な思考が欠かせません。
芥川龍之介もまた、文芸家志望の若者にこう語っています。
「文芸家たらんとする中学生は、須らく数学を学ぶ事勤勉なるべし。然らずんばその頭脳常に理路を辿る事迂にして、到底一人前の文芸家にならざるものと覚悟せよ。」
――文芸を志す者こそ、数学を学びなさい。そうでなければ論理の道筋を追う力が鈍くなり、一人前の文芸家にはなれない、と。
まさに、文と理がつながっていることを鋭く見抜いた言葉です。
これから文理選択を迎える中高生の皆さんへ。
自分の得意・不得意だけで早く結論を出す必要はありません。
「何が面白いと思えるか」「どんなことを考えていると時間を忘れるか」――その感覚を大切にしてください。
文系でも理系でも、最終的に求められるのは“自分の頭で考える力”と“自分の言葉で表現する力”です。
それこそが、文理の間にある力であり、高校卒業時までは文理科目を必須で学ばなければならない理由であると思います。